離婚の種類
協議離婚
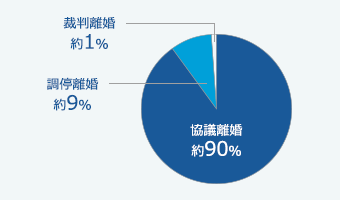
離婚件数の中でもっとも多いケースがこの協議離婚です。夫と妻、当事者間の話し合いによって離婚が合意できる場合の離婚方法です。パートナーとどのように交渉するかがとても重要となります。
しっかりとお互いの離婚への意思を確認し、離婚条件についてもしっかりと検討する必要があります。
それぞれ状況や環境、事情があると思いますので、一概には言えませんが、基本的に協議する必要がある事項としては、以下となります。
Point
協議する必要がある事項
- 親権者の指定
- 監護についての指定
- 養育費
- 面会交流
- 財産分与
- 慰謝料など
親権者の指定以外は離婚成立後でも決めることが出来ますが、また再び会って協議するというのは現実的でない場合が多いと思います。出来れば、離婚前に決めておいた方がよいと思います。
最も重要なことは、公正証書などを用いて、明確な形で協議内容をしっかりと確定しておくことです。
また、離婚届は、パートナーのみに渡すということはせずに、自分が離婚届を持つか、2通作成してお互いに提出できるようにしておくとよいと思います。
協議離婚の流れ
自分が知らない間にパートナーが「離婚届」を提出しても受理されないように出来る、「離婚届の不受理申出」という制度があります。不安な場合は活用しましょう。もし勝手に離婚届を出されてしまって受理されてしまった場合、戸籍が書き換えられてしまうため、調停での話し合いや、裁判所による判決を待つ必要があります。
01夫婦による離婚の話し合い(協議)
お互いの離婚の意思確認
離婚条件(未成年の子供がいる場合は親権・財産分与・慰謝料・養育費など)決定
![]()
02協議成立(離婚の合意)
協議内容(離婚条件)を文書にしておく。支払いが遅れたり、全く支払われなくなることが考えられますので口約束ではダメです。また、文書には「念書」・「離婚協議書」・「合意書」・「誓約書」などありますが、保管していたのに紛失してしまうことや、相手が勝手に作成したものだと言い逃れすることを防ぐため、「公正証書」やそれよりも強力で確実な「執行認諾文言付公正証書」にしましょう。
![]()
03離婚届の記入作成
離婚届の用紙に、当事者が署名・押印し、その上、証人として成人2人が署名・押印。それ以外に、未成年の子供がいる場合は親権者、離婚後の戸籍について記入。
![]()
04離婚届の提出
本籍または住民登録のある市区町村役場の戸籍係に提出。
![]()
05離婚届の受理
![]()
離婚成立
心情的に別れることを優先しがちですが、離婚条件をしっかり確認し文書にすることが大切です。
※当事者での話し合いがまとまらない場合やパートナーが話し合いに応じない場合、離婚を迷っている場合、関係を修復したい場合は「夫婦関係調整(離婚)」調停を申し立てます。
調停離婚
夫と妻、当事者間の話し合いによって離婚が合意できなかった場合や当事者間の話し合い自体ができる状況でない場合、調停といって家庭裁判所に申し立てることになります。
制度上、すぐに裁判に訴えることは出来ません。(「調停前置主義」)
調停とは、紛争解決のために調停委員などの第三者が当事者間に入って仲介し合意による解決を目指すというものです。
調停を申し立てる場合、「調停申立書」を作成して、家庭裁判所に提出する必要があります。
Point
調停申立書の記載事項
- 同居開始時期および別居開始時期、子供の有無、生年月日など当事者にかかわる事実
- 離婚原因
- 親権に関する事項
- 養育費に関する事項
- 財産分与に関する事項
- 慰謝料に関する事項
- その他
また、別居しており、居住先を知られたくない場合はその意思を伝えること。
パートナーから十分な生活費をもらっていない場合には、婚姻費用の分担を求めることも大切です。
調停は、一度で終わることは稀で、一般的には3~4回、間隔は1~2か月程度空くことが想定されます。
調停委員などの第三者が当事者間に入って仲介しますが、あくまで当事者間の合意による解決を目指します。
調停離婚の流れ
家庭裁判所にて、当事者間に調停委員などの第三者が入って仲介し、紛争解決を目指します。「離婚を前提にしたもの」・「修復を前提にしたもの」の2種類があります。 尚、相手の理由などは関係なく、「調停申立書」を提出した申立人以外、調停を取り下げることは出来ません。
01当事者間で協議をしたものの合意できず協議が不成立
![]()
02「調停申立書」を作成し、家庭裁判所に提出
パートナーの住居地にある家庭低裁判所です。
![]()
03調停申立の受理
![]()
04当事者に呼び出し状
調停が行われる日時は家庭裁判所が指定します。
- 出頭できない場合代わりに代理人や弁護士を出頭させることが出来ます。ただし、弁護士以外は家庭裁判所の許可が必要です。
- パートナーが出頭してくれない場合出頭勧告や制裁金(5万円の罰金)。最終的には調停取り下げや調停不成立となります。勿論、パートナーに対する心証は悪くなります。
パートナーに現住所を知られたくない場合や暴力などによりパートナーと顔を合わせることに支障がある場合、事前に申請しておくと、時間をずらすなどの手段を講じてくれます。
![]()
05調停
![]()
06調停成立
調停を重ね、話がまとまり合意すると裁判所が調停調書を作成し、調停が成立します。
![]()
07離婚届の提出
申立人は、離婚成立後10日以内に離婚届(パートナーの署名・押印は不要)を提出します。
![]()
離婚成立
※離婚の意思は合意しているものの、条件面で折り合いがつかない場合などは、「調停不成立」となり、家庭裁判所に離婚の審判を仰ぐことになります。
裁判離婚
家庭裁判所での調停でも解決出来なかった場合、裁判を起こすことになります。
まず5つの離婚原因のうち1つ以上にあてはまる必要があります。(>5つの離婚原因について)
裁判離婚では、協議離婚・調停離婚の2つとは違い、当事者間の合意がなくても裁判所が判決によって強制的に離婚を成立させることが出来ます。つまり、異論があっても離婚するかどうか、条件についても決着します。
また結婚生活の継続が望ましいとの結論によって、離婚を認めないといった判断をすることもあります。
裁判離婚の手続きは、法的書面の作成など、調停と比べて複雑になります。
一般的には、調停で合意できず、裁判離婚まで進んだ場合、決着がつくまでに1年またそれ以上かかることもあります。
裁判離婚の流れ
裁判では、訴えを起こした方を「原告」起こされた方を「被告」と呼びます。訴えを起こされた側は、答弁書を提出。口頭弁論、本人尋問や証人尋問、証拠調べなどの審理が行われ、離婚の可否を決定します。離婚請求や慰謝料、財産分与、養育費などの請求もできます。また、未成年の子供がいる場合は、親権者を決めます。
裁判では、民法で定められている5つの離婚原因のいずれかに当てはまることが証明されないと離婚は認められません。
離婚が認められれば、どんなに否定しても離婚は成立します。
01調停不成立
審判離婚に異議申し立てする。
![]()
02家庭裁判所に訴状を提出
離婚したい側が、家庭裁判所に訴える。離婚請求と同時に各請求もできる。
![]()
03訴状の通達
当事者に裁判期日の指定・呼び出しが通達される。※期日は裁判所が指定します。
![]()
04離婚裁判
調停が行われる日時は家庭裁判所が指定します。
- 請求認諾被告が原告の訴えを全面的に認める=認諾離婚
- 和解勧告当事者が歩み寄り和解する=和解離婚
パートナーに現住所を知られたくない場合や暴力などによりパートナーと顔を合わせることに支障がある場合、事前に申請しておくと、時間をずらすなどの手段を講じてくれます。
![]()
05判決
裁判後、約1か月で判決がでます。
- 勝訴被告が原告の訴えを全面的に認める=認諾離婚
- 敗訴当事者が歩み寄り和解する=和解離婚
尚、裁判所は、離婚原因がある場合でも、婚姻の継続が相当と認める時は離婚の請求を棄却することが出来る。

